この記事はほんの数分で読めます…が、得られるものは何もありません。
引き返すなら今のうちですm(_ _)m

なんでその年で卓球やってるんですか?
時々聞かれる質問です。
仕事にすら打ち込んでいない人が多い中で、仕事だけでなく卓球にも打ち込んでいて物珍しかったり、いい歳して何やってんだか…と嘲笑が含まれていたり。
角度は様々ですが、確かに珍しいかもしれませんね。
でもマーケターとして活動する僕の人生において、卓球は切っても切れない存在なんです。
なぜ29歳になった今でも現役選手として卓球を続けているのか。
なぜ仕事に集中せず卓球にも時間を割いているのか。
その理由を、今回はある程度真面目にお話ししようと思います。
※この記事は2025年6月時点での状況をもとに書いています。卓球歴や実績などの数字は当時のものです。
高校からの卓球歴と現在に至るまで

オワコン過ぎるスタートダッシュ
僕が卓球を始めたのは、高校で引退まで残り半年というタイミングから。
卓球部の顧問の先生とのやり取りは今でも鮮明に覚えています。
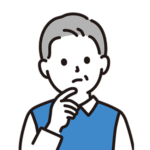
このタイミングで入部…!?
引退まであと半年も無いけど大丈夫?

はい大丈夫です、イケると思います。
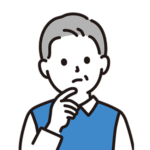
この時期にその自信ってことは経験者なの?

いえ、未経験です。
でも、なんかイケる気がします。
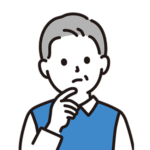
えぇ…

(……?)
なんてやり取りから、僕の卓球人生は始まりました。
ちなみに高校引退まで半年というのは、かなり遅いスタートです。
大半の選手は中学校から、早い人は小学生やそれ以前から始めるのが普通ですから。
きっかけは、元々中学でやりたかったバドミントンの代替案でした。
結局中学でバドミントンはできず、高校ではバドミントン部がなく…
「まあ、似たようなものかな」という軽い気持ちで卓球部の門を叩いたんです。
動画でプロの試合を見て「これなら自分でも天下を取れるかも」と思ったのも理由の一つ。
今思えば、完全に甘い考えでした。
卓球を甘く見て、斜に構えて参加した入部初日。
ラケットにボールを当てることすら困難で大恥をかいたのは、ほろ苦い思い出…なんて生ぬるい表現では片付けられない黒歴史です。

卓球、半端ないって!
動画で見る分にはボールめっちゃゆっくり見えるもん!そんなん自分にもできると思うやん!
なのに実際スピードもエグいし回転もエグいし…
言っといてや!そんな難しいスポーツやったら……
後に、そう必死に言い訳をする本庄弘大の姿があったとか無かったとか…
ブランクの方が圧倒的に長い絶望的な卓球キャリア
そんなこんなで卓球を始めてから12年ほど経過していますが、実際の卓球歴は2〜3年程度。
高校で半年、大学で1年半、そして今年から再開して5ヶ月です。
驚くべきことに、卓球歴よりもブランクの方が圧倒的に長い。
高校から浪人期間を経て大学までで1年半、大学から今年までで約8年のブランク。
大学時代に1年半で早々に2度目の卓球人生が終わった話は以下で触れています↓
運動が得意ではない僕にとって、ブランクの長さは致命的です。
正直ブランクが長すぎて卓球の技術の完全消失はもちろん、卓球が1ゲーム11点マッチであることすら忘れ去って、毎回0からのスタートを切っている感覚です。
なので僕が本来卓球を連続して2〜3年続けていた世界線の僕と比べると、今の僕は大きく劣り、トータルで同じくらい卓球をやっている人たちに対してすら分が悪いレベル。
個人事業主として基盤を固めることが最優先だったとはいえ、パッと見ると卓球へのやる気が感じられない舐めたキャリアですね。
それでも、なぜ卓球を続けるのか?

答えは単純です。
卓球が僕に与えてくれるものが、トータルで見ると他では得られないから。
普段は家に引きこもって仕事をしている僕にとって、卓球は人との関わりを持てる重要な場です。
外界から遮断された生活の中で、唯一と言っていいほど人とのリアルなコミュニケーションが取れる貴重な機会なんです。
普段は強がって言いませんが、ずっと一人でPCをカタカタする生活を送っていると寂しくなってくるので。
あと徐々にコミュ障が加速していくのを感じて不安になります。
また、卓球で強くなるという名目で日常に最低限のフィジカルトレーニングを取り入れることができており、これが体型維持、身体能力の向上、体力向上による仕事の生産性アップなど、様々な恩恵をもたらしてくれます。
自己肯定感の向上にも一役買っているのは否定しません。
現状県内だけで見ても、僕より格上の選手の数が圧倒的に多いので、仕事で上手くいっても天狗にならず「自分はまだまだ」と向上心を持ち続けることもできています。
謙虚さを保つ装置として機能している面もあるわけです。

卓球、半端ないって。
そして何より、純粋に楽しいんです。
大人になると「純粋に楽しい」と感じられることって、意外と少なくなりませんか?
もちろん、卓球と仕事には共通点も多く、互いに良い影響を与え合っている実感もあります。
この相乗効果については、また後ほど。
短期間で成果を出すための独自アプローチ

多くの人は「趣味と仕事の両立」というと、毎日少しずつ、あるいは平日の仕事後や休日に時間を割いて継続することを想像するでしょう。
僕は…まあ、そんなに器用じゃないので真逆のアプローチを取っています。
卓球歴2〜3年の初心者が、卓球歴10年を軽く超えるライバルたちとどう戦うか。
普通にやってたら勝てるわけないので、何か策を考えないといけませんよね。
限られたリソースを効率的に使う「集中と選択」の考え方は応用しています。

詳細は企業秘密ですが、自分より上級者を超えていく策がいくつかあります。
たぶん。
まだ今のところ施策を試し始めた段階ですが、社会人として卓球を始めて5ヶ月が経過した今、練習試合や大会でも少しずつ勝てるようになってきました。
今年に入って2ヶ月ほど、お金を払って県上級者のレッスンを受けた効果もあり、長年のブランクを埋めて以前よりレベルアップしている…と自分では評価しています。
1%以下の圧倒的少数派な戦型とこだわり

フォア面アンチラバーという異端
ここで僕の卓球におけるもう一つの特徴をお話しします。
僕は(大した調査もしていない本庄弘大の独自調査によると)卓球人口の1%以下の、非常に珍しいラバーの組み合わせを使っています。
フォア面に回転がほとんど掛からないアンチラバーを使用しているんです。
卓球を知らない方に簡単に説明すると、一般的にはフォア面(利き手側)には回転がよく掛かる裏ソフトというラバーを使います。
アンチラバーは使うとしてもバック面(聞き手と反対側)で、しかも攻撃よりは変化をつけて相手のミスを誘ったりチャンスメイクに使うのが普通です。
ところが僕は、そのアンチラバーをフォア面に使い、積極的に攻撃するスタイルを取っています。
回転が掛かりにくいアンチラバーで申し訳程度に回転を掛けたドライブ攻撃も良く使います。自分で言うのもなんですが、これは珍しいやり口だと思います。
所見では面食らう人が多い。
差別化戦略としての合理性(笑)
なぜこんな変則的な組み合わせを選んだのか?
理由は二つあります。
一つは性格的な面。他と同じことをしたくないという僕の根本的な性格と、異質ラバーを使いたいという気持ちです。
フォアアンチにも慣れてきた今となっては、他と同じ両面裏ソフトにするくらいなら卓球を辞めるくらいの気持ちです。
もう一つは合理的な判断。
僕は卓球歴2〜3年で、周りは10年以上の選手ばかり。
それどころか20年も30年もやっている人もいて、10年でも可愛いくらいです。
普通のことをしていては勝つのは難しいというのが現実です。
それなら、相手が慣れていない変則的なスタイルで勝負する方が合理的だと考えました。
この考え方も、マーケティングと通じるものがあります。
レッドオーシャンで真正面から勝負するのではなく、ブルーオーシャンを見つけて差別化を図る。
小さな会社が大手に勝つための戦略と同じですね。
まあ、それっぽいことを言いましたが、取り繕わず正直にいうと、僕がセオリーとか無視して、勝算が十分に残る範囲内で好きにやってるってだけですけどね。

考えるべきところは考えないと成果は出せませんが、あまり堅苦しく考えすぎても面白くなくなりますよね。
ちなみに僕が仕事でクライアントのマーケティング支援をする時なども、このスタンスを採用することが多いです。
成果が出る範囲からは逸脱しないものの、自分らしくやれる範囲を見つける。
ここを外さないようにするので、お互いの満足度は高いわけです。
卓球と仕事の意外な共通点

相手を分析して戦略を立てる
この卓球への取り組み方は、実は僕の仕事と似ている部分があります。
卓球では相手の癖を読み、弱点を見つけて、どう攻めるかを考えます。
これってマーケティングでやる市場分析や競合分析と全く同じなんです。
たぶん。
とはいえ、普段のマーケティング業務では自分なりの仮説を立てるまでに、それなりに時間をかけて考えることができるのに対して、卓球では非常に短い時間で判断する必要があります。
卓球が不慣れな僕にとっては、仕事より遥かに難易度が高いんですけどね。
汎用的スキルの検証実験
個人事業主として仕事をする中で身につけた「考える力」や「成果を出す力」は、卓球でも活かされている気がします。
目標設定、PDCAサイクル、効率的な学習方法など、ビジネスで培ったスキルが競技面でも役立っているんです。
というか、これらの力は分野が変わっても共通して使える汎用的なスキルである…というのが僕の持論なので、卓球をやるのは、この仮説の検証でもあるんですよね。
独自のやり方を考案して実践し、成長して成果を出していくプロセスが大好きなので、常に自主的に取り組むことができています。
逆に、卓球を通じて身につけた集中力や判断力なども、日々の仕事に良い影響を与えてくれていると感じます。
卓球と仕事、両方やっているからこそ得られる相乗効果があるんです。
この相乗効果こそが、僕が29歳になった今でも現役選手として続けている大きな理由の一つでもあります。

というか、この年で何の相乗効果も産まないことをやる余裕は無い…
現在の活動と今後の目標

チームでの活動と成果
現在、僕は沖縄の卓球チームの一員として活動しています。
実は僕が通っていた大学のOBの先輩が作ったチームで、OBの先輩に得意の土下座と靴舐めを経て加入させてもらったという経緯があります。
チーム内では「唯一の初心者」としてブランディング(笑)しており、メンバーとの関係も良好です。
たぶん。
最近では沖縄の団体戦にCチームとして4部で出場しました。
ちなみに僕が所属するチームは、団体戦では実力別にA〜Cの3チームで編成されており、僕は当然ながら一番下のCチームに配属されています。また団体戦は男子の場合、レベル別に1部〜7部までの大会が開かれ、数字が小さいほど強いです。その中で僕たちCチームは4部の大会に割り振られました。
相手は正直あまり強い選手ではありませんでしたが、チームに入って初めての大会で、準決勝でストレート勝ちを収めてチームの勝利に貢献。
結果として準優勝することができました。
準優勝により次回から3部に昇格となったので、僕のせいでチームが降格…ということにならなくて良かったです。
大学時代の僕であれば、大人しくストレート負けして、敗北コレクターの名を欲しいままにしていたと思うので、かなり嬉しかったです。
まあ直後の決勝戦では、僕が負けたせいでチームを敗北に導いたわけなのでプラスマイナス0ですけど。
今後の目標
競技面では、沖縄No.1のフォアアンチの地位を確立すること。
沖縄でフォアアンチのプレイヤーは僕が知る限り2〜3名程度しかいないので、このまま戦略的に続けていれば、いずれNo.1になれるはずです。
母数が少ないという事実を活用した、ある意味で非常に合理的な目標設定です。
まあ割とギャグ要素としてですけどね。
ちなみに実力的には、県ベスト8常連を目指しています。

なんかイケる気がします。
仕事面では、引き続き卓球と仕事、ひいては人生単位で相乗効果を生み出していきたいと考えています。
そして今後も卓球を義務ではなく純粋に、僕の人生を彩るスパイスとして楽しんでいけたらなと思います。
切実に。
29歳で卓球を続ける理由

なぜ僕が29歳になった今でも卓球愛好家として活動を続けるのか。
それは、どちらか一つでは得られない価値がそこにあるからです。
卓球を通じて人とのリアルなコミュニケーションが取れて、体力も向上し、謙虚さも保てる(たぶん)。
仕事では分析力や論理的思考が鍛えられ、卓球での経験も活かされる。
そして両方を組み合わせることで、どちらも単体でやるより高いレベルに到達できている実感があります。
仕事だけに留まらず、人生レベルで向き合っていることがあるからこそ、より豊かな人間になれると信じています。
僕にとって卓球は、そんな充実感を与えてくれる貴重な存在なんです。

さて、卓球歴2〜3年の初心者が10年以上卓球経験があるライバルばかりの環境で、どこまでやれるか…非常に見ものですね。
ここまで記事を読んでいただき、ありがとうございました!
良ければ引き続き、僕のモノローグをお楽しみください↓
仕事寄りの記事はこちら↓



